promotion
生活には音がつきものです。
車のエンジン音、工事の音、隣人の話し声、また自分たちが発する音もあるでしょう。
楽器を奏でる音、テレビの音、子供の遊ぶ声。
しかし音は一定のレベルを超えると騒音になってしまいますよね。
騒音を少なくすることは快適に生活するためには大事なことです。
また今はプライベートを大事にする時代、一戸建てに住むのならお互いに音を気にしない生活を望む方も増えていますよね。
ハウスメーカーを選ぶ基準に防音性を挙げている方は、音によるストレスを少なくしたいと考えている方がほとんどでしょう。
しかし住宅の防音については情報が少ない事もあり、どのように防音対策をすれば良いか悩むと思います。
また音を騒音と感じるレベルは人それぞれなので対策の難しい部分です。
そこでこの記事では、住宅業界では非常に情報の少ない防音性について解説すると共に、防音に力を入れているハウスメーカーを紹介していきます。
また本文に入る前に、家づくりにおいて1番重要なことをお伝えします。
家を建てるときには、まず出来るだけ多くの住宅メーカーのカタログや資料を取り寄せて下さい。
これから先、何年、何十年と大切な家族と住むことになるマイホーム。
絶対に失敗をするわけにはいきません。
実際に、住宅展示場やイベントで見つけた5,6社程度の検討で住宅メーカーを決めてしまい、後から取り返しのつかない後悔をする方は少なくありません。 
マイホームは多くの人にとって、人生で1回だけの最も大きな買い物の一つ。
極端な話、マイホームを建てようと思っているエリアに対応している住宅メーカーは全て候補にいれ比較検討するくらいの勢いで構いません。
しかし、1社1社話に資料請求をしたり話を聞いて回るのは現実的ではありませんよね。
そこでおすすめなのが、「SUUMOの無料カタログ一括取り寄せ」(工務店中心)と「NTTデータグループ家づくりのとびら」(ハウスメーカー中心)。
スマホから住んでるエリアと条件を選ぶだけで条件に合った住宅メーカーから、無料でかんたんに資料を手に入れることができます。
2社とも日本を代表する上場企業ということもあり、登録している住宅メーカーを激選しているのも大きなポイント。
住宅メーカーの中には悪質な会社も多く存在しますが、厳しい審査をクリアした会社のみ掲載が許されているので悪質業者の被害にあうリスクや強引な営業も避けられるのは大きなメリットでしょう。
SUUMOは工務店を中心に、NTTデータグループはハウスメーカーを中心に取り扱っています。
最初は候補にもあがっていなかった住宅メーカーが実は1番自分たち家族にはあっていたというケースは多いです。
「自分たちの予算ではハウスメーカーは無理だから・・・。」
「有名ハウスメーカー以外は考えられない!」etc...
このように先入観を持つのではなく、可能な限り多くの住宅メーカーを検討対象にすることで失敗しない家づくりの確率は高められます。
後から取り返しのつかない後悔をしないよう、面倒くさがらず今すぐ住宅メーカーの資料を取り寄せてしまうことをおすすめします。 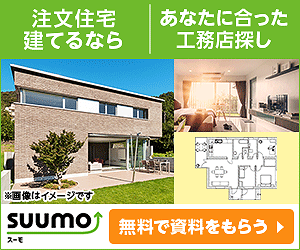
SUUMOで無料カタログ取り寄せはこちら⇒(工務店中心) 
家づくりのとびらで無料カタログ取り寄せ⇒(ハウスメーカー中心)
それでは解説をしていきます。参考にして下さい。

【本記事の監修者】 宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー 大学卒業後、東証一部上場大手保険代理店へ入社。その後、大手不動産ポータルサイト運営会社へ転職。ITベンチャー企業での経験を経て株式会社Azwayを創業。 「住まい」と「ライフスタイル」に特化したWEBサービスを手掛けている。
もくじ
ハウスメーカーの定義

はじめに防音に力を入れているハウスメーカーを紹介するにあたって、ハウスメーカーとは、どの規模の建設会社なのかを説明します。
ハウスメーカーは日本国内のほぼすべての地域で、同じ規格の材料を使って同等の性能の家を建てられる建築会社の事を表すと考えてよいでしょう。
同時に規格をそろえる為に工場を持ち、工場内で壁などの各パーツを組み立て、現場での組み立てを少なくする工法が多い事も特徴です。
また、国が出している住宅の性能基準、環境基準にいち早く対応している建築会社でもあります。
その為の研究施設なども別に持っている場合がほとんどですね。
ハウスメーカーのデメリットは本来の家を建てる部分以外のコストがある為、坪単価が高くなってしまうことではないでしょうか。
しかし、ハウスメーカーはこの様な組織の大きさと研究から導かれた確かなデータを基にした住宅性能などで、地場の工務店にはない信頼性がある建築会社であると言えます。
建築会社の全国展開の方法としてフランチャイズ、FC展開方式があります。
この方式は親会社と実際に建てる建築会社の経営が別々となり、加盟店契約を結ぶことによって親会社の技術と名前を使って加盟店が家を建てる方式なんですね。
ハウスメーカーとは少し違いますが、全国展開しているフランチャイズ形式の建築会社も広い意味ではハウスメーカーと言っていいでしょう。
実はハウスメーカーという基準は非常にあいまいでしっかりした基準がありません。
ですので、この記事では上記を目安としてハウスメーカーの防音性について解説していきます。
防音対策にこだわっているハウスメーカー5社を紹介

今回紹介するハウスメーカーは元断熱・気密技師の筆者が現場サイドから見た場合に「しっかり防音を考えているな」と思えるハウスメーカーを紹介しています。
「断熱・気密技師に防音がわかるの?」と思うでしょう。
後でも説明しますが防音と断熱・気密は密接なつながりがあるのです。
ですので、防音性を高める為に私達断熱・気密技師に依頼が来ることも多く、音楽業界で防音に携わる方には及びませんが、一般住宅の防音性に関しては技術と知識を持っているわけです。
今回ここで紹介するハウスメーカーは、個々の部材の防音性能はあまり選定基準にしていません。
選定基準にしている部分は住む人が求める防音性能を作りやすい建物か?という点です。
住宅の防音は建物全体で作る性能なので、基本的な建物全体の性能が防音向きか?という点に焦点を当てているわけですね。
ですので、一般のおすすめとは若干変わる可能性がありますが、一つの考え方と捉えて参考にしてください。
ミサワホーム
ミサワホームの「木質パネル接着工法は」防音性の高い工法としておすすめです。
気密性も高く隙間からの音漏れも少ないでしょう。
また、ミサワホームは下の階に音の伝わりやすい上階の床防音にも力を入れています。
オプション仕様ですが、3種類の防音性能が違う床構造があり、予算と求める性能に合わせた工法を選ぶことが出来るでしょう。
室内の壁つまり間仕切りの防音についてもオプション設定があることもポイント。
窓も十分な防音性能をもったサッシを使用しているので問題ないでしょう。
ただミサワホームの宣伝では大きな窓をPRしています。
窓はいくら防音性能が高くても外部に接している部材の中では一番防音性能が低い部分。
道路側など防音を強化したい面の窓を少なくするなどの配慮をすれば、更に効果が上がるでしょう。
スウェーデンハウス
スウェーデンハウスは断熱性、気密性、そして北欧風のデザインが人気のハウスメーカーです。
スウェーデンハウスの外周構造を見ると、基本的な防音性能は十分備わっていると判断できます。
壁や屋根の高い断熱性がそのまま防音性につながる構造になっていました。
サッシについては日本では珍しい木製のサッシ枠。
木自体の防音性が高いので非常に防音対策に貢献するでしょう。
3重ガラスも防音性能が高い部類に入りますね。
床対策や間仕切り対策は基本仕様がないので別で依頼する必要がありますが、防音の基本性能が高い住宅を普通に建てているハウスメーカーと言えるでしょう。
セルコホーム
セルコホームはフランチャイズ方式でカナダ輸入住宅を建てている会社です。
セルコホームの場合は2×6(ツーバイシックス)工法の防音性能が高いですね。
2×6工法の場合、壁の断熱材が高性能グラスウール140㎜。
外壁や内側の石膏ボードと合わせれば十分な防音性能を発揮します。
ですが現場で断熱材を入れる作業になる為、若干職人の技術に左右されてしまう点はデメリット。
窓についても4種類のサッシを準備しているので予算に合わせて選択できます。
床の防音は独自の技術で高い防音性を確保している点がセルコホームを選んだ理由の一つ。
ベースがあるので更に高い防音性能を作る事が可能でしょう。
フランチャイズで全国展開している中では防音性がトップクラスに入るハウスメーカーではないでしょうか。
ユニバーサルホーム
木造在来工法の中でも強度が高い金物工法で全国展開しているユニバーサルホーム。
ユニバーサルホームもフランチャイズ展開のハウスメーカーです。
ユニバーサルホームを選んだ理由は現場発泡ウレタン断熱とALCの外壁により、外部からの音を大きく遮断できる可能性のあるハウスメーカーだからです。
現場発泡ウレタンとは、現場で2つの液体を混合させて壁や屋根に内側から吹き付け、化学反応で発泡させて断熱を行う工法なんですね。
使用しているウレタンは水発泡ウレタンもしくは高発泡ウレタンと呼ばれ、フロンを使用しない環境にやさしいウレタンです。
しかも柔軟性があり木造住宅に最適なウレタンと呼ばれています。
このウレタン施工により隙間のない断熱が容易に可能で、同時に防音性も確保できるわけです。
そして厚さ37㎜のALC外壁材。
ALCは軽量コンクリートとも呼ばれ、重鉄骨造ビルの外壁に使われることが多い材料です。
特徴がその厚さだけではなく多孔質構造による断熱性と防音性。
サッシも高性能のペアガラス樹脂枠サッシを使用しているので、外の音に対する防音の基本性能は十分と言えます。
家の中の防音対策は特に準備していないので、各加盟店での追加工事扱いになるでしょう。
木造在来工法は自由度の高い建築が可能な工法なので、木造在来工法の家を考えている場合はユニバーサルホームを候補に加えてはどうでしょうか。
ダイワハウス
最後に皆さんもよく知っている、ハウスメーカー最大手のダイワハウスを紹介します。
ダイワハウスは木造在来工法と鉄骨造の2種類の工法を持っていますが、どちらも外断熱と内断熱の併用で防音性を発揮できる構造になっています。
特に鉄骨造は「考えているな~」と感心する構造ですね。
通常の鉄骨造は鉄でできた柱部分が熱や音を通してしまい断熱性や防音性が低くなる傾向があります。
ですがダイワハウスはその鉄骨部分を上手に保護する構造になっていました。
木造住宅やRC造(コンクリート造)には劣るものの、鉄骨造の中では防音性の高い家を建てられるハウスメーカーでしょう。
ただ、複雑な構造なので職人・大工の技術と慣れが必要な点はデメリット。
ダイワハウスを選んだ理由はオプションで防音室を作る事ができる点です。
防音室は防音に対する高い知識と技術が必要ですから、ダイワハウスが防音に対するノウハウを持っている証明になります。
防音室を作らないまでも、その技術を利用して1部屋だけ防音を強化するなどが容易にできるハウスメーカーと考えていいでしょう。
床の防音も標準仕様で可能な点などをみても、ダイワハウスは鉄骨系ハウスメーカーの中では1番防音にこだわっているハウスメーカでしょう。
音の基礎知識を知っておこう

防音対策にこだわっているハウスメーカーを紹介しましたが、最終的に判断するのは読者のみなさんです。
しかしみなさんが防音について知識が無ければ判断できませんよね。
ここではみなさんがハウスメーカーの防音性を判断するための防音の基礎意識を解説していきます。
音の伝わり方は2通り
家の防音を考える場合、音は「空気伝搬音」と「固体伝搬音」の2種類あることを知らなければいけません。
空気伝搬音は例えばサイレンの音や話し声などの空気を伝わる音の事です。
固体伝搬音とはマンションで上階の歩く音が聞こえたり壁を叩いたりした時に物を伝って聞こえる音の事をいうのですね。
家などの建物の場合、空気伝搬音は比較的防音しやすいのですが固体伝搬音を少なくする事は難しいと考えてください。
話し声やサイレンの音、楽器の音などは防音しやすくても壁をドンッと叩く音は防音しにくいと思っていいでしょう。
また、住宅の場合は空気伝搬音を防音する方法と固体伝搬音を防音する場合では防音対策が別々になり固体伝搬音を防音する技術の方が難しいと覚えておきましょう。
音質の違いによる防音性能の違い
音質とは高音、低音の違いを指し「Hz(ヘルツ)」という単位で表されます。
Hz(ヘルツ)で音質を表した場合、人間が聞くことのできる音域(音の幅)は20Hz(低音)~20,000Hz(高音)と言われているのですね。
音質の違いつまり高音と低音では防音性能に違いが出てきます。
カラオケボックスで廊下を歩いているとドラムのリズムは聞こえるけどメロディは聞こえないなどを経験したことがあるでしょう。
ドラムの音は低音、メロディは基本高音に分類されます。
つまり低音は防音しにくいのですね。
生活音の中で低音は高音の半分程度しか防音できないと言われています。
次に説明する音のレベルとも関係してくるので、次でもう少し詳しく説明しましょう。
音のレベルを知って防音対策に役立てよう
音のレベルつまり音量または音圧は「dB(デシベル)」で表します。
dB(デシベル)はみなさんも聞いたことがあるでしょう。
騒音の高さや防音性を表す数値として一般dB(デシベル)が使われているのですね。
一般的な基準になりますが、音dB(デシベル)で表した場合、下記の分類に分けることが出来ます。
| 音のレベル(目安) | dB | 音源例 | 人への影響 |
| 極めてうるさい | 120 | 飛行機のエンジンの近く
近くの落雷 |
聴覚機能に異常をきたす場合がある |
| 110 | 自動車のクラクション | ||
| 100 | 電車が通るガード下
地下鉄の構内 |
||
| 90 | カラオケ音(店内)
犬の鳴き声(直近) 工場の中 |
うるさくて我慢できない | |
| 80 | 走行中の電車内
救急車のサイレン(直近) パチンコ店内 布団たたき ピアノ |
||
| うるさい | 70 | 高速走行中の自動車車内
セミの鳴き声(直近) 騒々しい街頭 |
かなりうるさい
大きな声を出さないと会話が成立しない |
| 60 | 走行中の自動車内
普通の会話 デパート店内 トイレの洗浄音 テレビの音 洗濯機 |
非常に大きく聞こえうるさい
声を大きくすれば会話可能 |
|
| 普通 | 50 | 家庭用エアコンの室外機
静かな事務所の中 換気扇 |
大きく聞こえる
通常の会話は可能 |
| 40 | 閑静な住宅地の昼
図書館内 市内の深夜 |
聞こえる
会話に支障なし |
|
| 静か | 30 | 深夜の郊外
鉛筆での執筆音 |
非常に小さく聞こえる |
| 20 | 木の葉の触れ合う音
雪の降る音 小さな寝息 |
ほとんど聞こえない |
この表を見ると、自分はうるさく感じない音が「うるさい」や「極めてうるさい」に入っている方はいますよね。
このように音は人それぞれで感じ方が全く違うのです。
そこで、dB(デシベル)を基準に防音を考える場合、環境省が発表している「騒音に係る環境基準」を参考にするといいでしょう。
| 地域の種類 | 基準値 | |
| 昼間 | 夜間 | |
| 医療施設、社会福祉施設が集合して設置される地域 | 50dB(デシベル)以下 | 40dB(デシベル)以下 |
| 住宅地域 | 55dB(デシベル)以下 | 45dB(デシベル)以下 |
| 商業、工業地域 | 60dB(デシベル)以下 | 50dB(デシベル)以下 |
この基準を参考に家の中が「55dB以下になるように」などと目安をつけるといいでしょう。
例として、家を建てる周りが平均70dB(デシベル)の騒音があり、家の中を50dB(デシベル)以下にしたい場合、20dB(デシベル)の防音対策をすればいいとなるわけですね。
ちなみに普段の生活では静かだと思っても30dB(デシベル)程度の音は常に聞こえていて、30dB(デシベル)以下になるとかえって不安になってしまうそうです。
また先ほどのHz(ヘルツ)と係わって来る部分なのですが、dB(デシベル)は通常中音域の500Hz(ヘルツ)付近を基準にしています。
ですから、家の中が50dB(デシベル)に保たれていたとしても低音域の音は聞こえやすく、高音域の音は50dB(デシベル)の防音効果よりさらに聞こえにくいと考えてください。
基本的な防音対策

音の防音は先ほど話したように、人それぞれで騒音に感じる音が違うため「これがいい」と断言できる方法がありません。
ですので、ここでは一般的な防音対策のポイントを解説していきます。
「どの音をどうしたいか」を考える時の目安にしてください。
防音対策は何をする?
防音対策といっても実は音の種類によって対策の仕方が違ってきます。
具体的には「遮音(しゃおん)」、「吸音」、「防振」、「制振」の4つの対策があるのですね。
この4つの対策について最初解説します。
空気伝搬音を防音する「遮音」、「吸音」
はじめに遮音とは音をさえぎる対策のことを言います。
音をさえぎる為には、音をさえぎる物体が厚くて密度が高いほど効果が高くなります。
コンクリートの壁と木の壁で同じ厚さの場合、コンクリートの壁の方が遮音性が高くなるわけです。
ただ遮音性ばかりが強いと、音が跳ね返って不快な音になるデメリットもあります。
同時に家の場合、壁の厚さにも限界があるので通常「吸音」と併用して防音効果を高めているのです。
次に吸音は音を吸収したり分散したりする材料を使って音の振動を弱める対策です。
劇場などで壁がデコボコしているのを見たことがあると思いますが、あれが吸音部材なんですね。
何もない部屋で自分の声が反射して聞こえたことはありませんか?
しかし、家具やカーテンを置くと気にならなくなりますよね。
実は何気ないこの事が吸音効果になっているのです。
カーテンも吸音効果がありますから吸音カーテンを閉めるだけで外の音が聞こえにくくなるのですね。
家の場合、繊維系の断熱材であるグラスウールやロックウールが吸音部材として使われています。
空気伝搬音の防音は遮音対策を行い、遮音対策の効果を上げる為に吸音対策をする考え方が効果的でしょう。
「防振」と「制振」は固体伝搬音を少なくする対策
防振と制振は簡単に言えば2階の床を足でドンッと蹴った音を1階に伝えにくくする対策です。
防振は出た音を防ぐ対策、制振は音自体を出さない対策です。
両方とも基本的には緩衝材つまり柔らかい部材を挟むことによって対策していますが、残念ながら住宅では100%聞こえなくすることは無理なんですね。
一般住宅での固体伝搬音の防音対策は、制振つまり物から出る音を建物に伝わりにくくする対策をメインに行います。
例えば洗濯機の足の下に制振マットを敷く、床をフローリングではなくカーペットにするなどですね。
そして建物に伝わってしまった音については床材の下のゴムマットや天井の下地に防振材を使うなどの対策で防振する方法が一般的です。
固体伝搬音対策は要約すると「音が出てほしくない場所で使う物」は「音の静かな物も使う」ことでしょう。
例として2階に洗濯機置き場を作らないことや子供のメインの遊びスペースは1階に設けるなど、ライフスタイルに照らし合わせて検討してみてもいいと思いますよ。
外部からの音に対する防音対策
外部からの音を防音する対策は家の断熱性、気密性と密接な関係があります。
先ほどお話したように断熱材は効果的な防音材ですよね。
つまり断熱材がしっかり厚く入っている事は断熱性が高いだけでなく防音性も高くなるわけです。
また、家の隙間が少なければ気密性が上がるわけですが、隙間が少ない事は音が漏れにくい事につながりますよね。
実は外部の騒音に対する防音性は、高断熱・高気密住宅を求めれば十分な防音性能を得られるのです。
今回紹介したハウスメーカーも、この点を選定基準の1つにしています。
以下では高断熱・高気密住宅を前提として「外壁」、「窓」、「屋根」の3ヶ所に分けて材料の使い方などのポイントを紹介しますので、ハウスメーカー選びの参考にしてください。
外壁
外壁は厚く密度が高い材料を使えば遮音効果が高くなります。
基本的に木材や鉄板よりサイディングの方が防音効果は高くなりますね。
また外壁内の断熱材についても発泡スチロール系やウレタン系よりもグラスウール、ロックウールなどの繊維系が吸音効果は高い傾向があります。
外壁を厚くすればそれだけ防音の効果が高くなりますが限界があるので、外壁材、壁の中の断熱材そして防音・遮音シートなどを使って総合的に防音する方法が一般的です。
窓
窓は防音性、断熱性共に一番低い部分になります。
防音を強化したい部分、例えば交通量の多い前面道路側の窓を小さく、数も少なくすれば家全体の防音性能は高くなるでしょう。
窓つまりサッシ自体も断熱性・気密性の高いペアガラス、三重ガラスそして樹脂サッシが防音性は高いですね。
コストを落としつつ防音性を高めたい場合は、ある程度の性能を持つサッシの内側にもう一枚窓を設置する2重サッシ+防音カーテンもしくは厚手のカーテンの形がおすすめです。
窓の配置は生活の快適性とも係わってきますから、最も防音したい方向に大きな窓がほしいリビングなどを配置しない工夫が必要でしょう。
屋根
屋根は主に雨音に対する防音がメインになると思います。
ただし、通常の傾斜のついた屋根でしたら断熱材がしっかり入っている高断熱・高気密住宅の場合、あまり気にしなくて大丈夫でしょう。
ですがバルコニーの下が部屋、または屋根ではなく屋上になっている場合は雨音や足音が気になる場合があります。
この場合の防音対策ですが、通常の断熱材の他にバルコニー防水の下地に制振・防振シートを挟んだり、天井の下地に制振材を使用したりする方法が考えられます。
大きなバルコニーを考えているのでしたら、防音の意外な盲点なので気を付けてくださいね。
建物内部で響く音の防音
外部からの音が少なくなった住宅では家の中で出る音が気になると思います。
特に夜は起きている時間も家族でバラバラでしょうからなおさらですね。
ここでは家の中の音を少なくするポイントを紹介します。
家の計画段階で防音を考える際の検討材料にしてください。
間取り
寝室や書斎などの静かにしたい部屋は、以下の点に気を付けて配置すると良いでしょう。
- 外の騒音が一番大きい方向(道路側)などを避ける
- トイレなどの水回りのすぐ脇やすぐ下は流水音が気になる場合がある
- ボイラーなどの設備機器の近くも固体伝搬音が気になる部分
- となりのお宅のボイラーやリビングなどの位置にも気を遣う
また、間取りとして吹き抜けやリビング内に2階への階段を設置した場合、音が他の部屋に響きやすくなります。
吹き抜けは解放感があり人気ですが、防音ではデメリットになる事を覚えておくと良いでしょう。
内壁
間取りだけでは不足の場合、壁内部に吸音性の高い繊維系の断熱材を入れる方法があります。
断熱材+防振・防音シートで大きな効果を得られるでしょう。
また、ドアにも気を使うと更に効果は上がります。
シアタールームやピアノなどの楽器を本格的に使うのでなければ、十分な効果が期待できますから検討してみてください。
床・天井
上階の床と下の階の天井はセットで考えた方が、効果が高いでしょう。
上階の床は制振を中心に考えます。
床材を制振性の高い材料、例えば柔らかい床材、クッションフロア、コルクカーペットにする。
床下地の下に制振マットやゴムマットを敷くなどの対策が効果的です。
本畳(イグサとわらで作った重い畳)も制震性は高いのでいいかもしれませんよ。
そして下の階の天井は、防振吊り木(天井の下地)と天井の上にグラスウールなどの断熱材を敷き込むことで防振効果が得られます。
2階から1階に響く足音などは家の中の音で一番気になる音ですが、一番防音しにくい音です。
静かにしたい部屋の上にうるさくなる可能性の部屋を配置しないなど、間取りの工夫と合わせて防音対策をすると、より効果があるでしょう。
防音は完全には難しい!どのレベルを求めるか検討しよう。

防音はここまで解説してきたように対策をすれば高い防音性は得られますが、その分コストがかかります。
ハウスメーカーでも金額的に通常家を建てるより150万円から300万円位建築費用が高くなると考えてください。
本格的な防音室を作るなら更に高くなる場合もあります。
しかし何度も話したように音は人それぞれで感じ方が違いますよね。
どのレベルの防音を求めれば良いか難しいでしょう。
そこで、防音性のレベルを確かめる為にハウスメーカーのモデルルームを見学する方法をおすすめします。
1つの部屋を借りて外の喧騒やとなりの部屋の音がどのように感じるか、自分の感覚で確かめる方法が一番いいでしょう。
今は携帯で「騒音」で検索すれ、dB(デシベル)を簡易的に測れるアプリがありますから、実際に外と部屋の中の音を計測する方法もおすすめですよ。
防音性能でハウスメーカーを選ぶ際、外の騒音に対しては高断熱・高気密住宅を基準にすれば基本的な防音性のが手に入ります。
そして家の中の音対策は、ハウスメーカーがオプションで防音商品を持っている、持っていないに係わらず、担当が間取りを含めた総合的な目であなたに防音を提案してくれるハウスメーカーを選ぶといいでしょう。
なぜなら防音は個々の部材ではなく、建物全体を考えなければ効果が低い対策だからです。
次でも話しますが、建物全体を考えた防音を提案する担当者は防音の知識があると判断し、信用して良いと思います。
防音について知識豊かな担当者に出会うことも、家の防音を考える上で必要なことではないでしょうか。
注意点!防音性は知識と施工技術に左右される

高い防音性を建てる家に望むのでしたら、ハウスメーカーのカタログススペックは目安にしかならないと思った方が良いでしょう。
ハウスメーカーの良さは均一の材料を全国で使って、同じ性能の家を建てられる事にあります。
ですがその材料を組み立てるのは現地の職人とスタッフですよね。
現地のスタッフつまり監督と職人がその材料の扱いに精通していなければ本来の性能はでないと思いませんか?
防音性を高める為には各部材の繋ぎ目や配管の穴などにも気を配る必要があります。
ですから監督に防音の知識が無ければ施工漏れなどのチェックができないでしょう。
良い家を建てる為には現場を重視しなければいけません。少なくともこの記事の内容を理解できない監督に、あなたの大切な家を建てる事を任せない方が賢明と思いますよ。
まとめ
家の防音性能は快適な生活を送る為の条件の一つ。
今回紹介したハウスメーカーは、これから家を建てようと考えている方が、音で悩まない防音性能を提供してくれる可能性があります。
しかし、音は人それぞれで感じ方が違うので、「このレベルの防音で大丈夫」とカタログ上で判断できない性能であることを認識しなければいけません。
ですが、家を建ててから「思っていたよりうるさい」を無くすために、まず施主であるあなたが知識を持つことが大切です。
同時に現地での計測、ハウスメーカーのモデルルーム見学などを通じて、自ら体験して納得する必要があるでしょう。
防音性能は非常に感覚的で難しい性能ではありますが、求めれば手に入る性能です。
ぜひこの記事を参考の一つにしていただき、自分にあったハウスメーカーを探し、納得のいく家を建てましょう。










コメントを残す